神奈川県で公立高校受験をするなら知っておきたいポイント
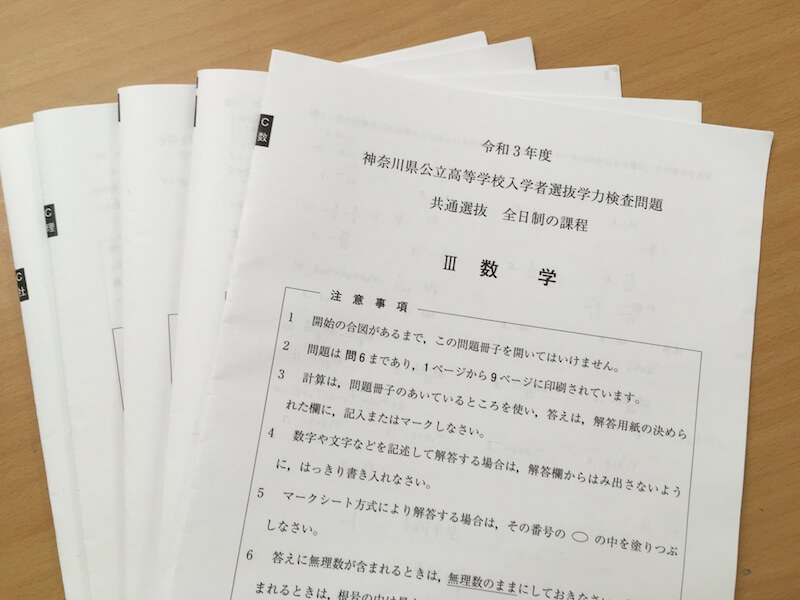
このページでは『神奈川県立高校選抜試験』の基礎知識をお伝えします。
1. 神奈川県立高校選抜試験の概要
まずは、ざっくりと神奈川県立入試の概要をつかんでおきましょう。
1-1. 試験内容
全員に学力試験が課されます。2024年から全高校での面接試験は無くなりました。
高校によっては特色検査(実技試験・自己表現試験・面接)を実施する場合があります。
学力試験
国語、数学、英語、理科、社会の5科目の試験で受験者全員が5科目受験します。
※一部の特色検査を実施する学校では3科目まで科目を減らすことがあります。
各科目ともに配点は100点で試験時間は50分です。
面接試験
2014年度から2023年度まで全ての受験生に面接試験が実施されていましたが、2024年から一律の面接試験は無くなり一部の学校で特色検査の中で実施されることになりました。
特色試験
一部の学校ではて自己表現検査または実技検査または面接が行われます。
例えば『文章や資料を読み取り、知識・技能を教科横断的に活用して、問題を解決する思考力・判断力・表現力や創造力等を把握するための検査』『提示されたテーマについての討議・スピーチ等』などがあります。
1-2. 試験や出願の日程
| 出願期間 | 2024年1月24日(水) – 1月31日(水) |
|---|---|
| 志願変更期間 | 2024年2月5日(月) – 7日(水) |
| 学力検査 | 2024年2月14日(木) |
| 面接・特色検査 | 2024年2月14日(水)、15日(木)、18日(金) |
| 追試 | 感染症などやむを得ない事情により受験できなかった生徒の中で希望するものに追試験を実施。一部の面接試験を除いて特色試験のつい試験は行わない。 |
| 合格発表 | 2024年2月28日(水) |
1-3. 出願方法
出願は「神奈川県公立高等学校入学者選抜統合型インターネット出願システム」を通じて行います。
- アカウントの登録にはメールアドレスが必要
- 詳細は2023年12月に発表される
- 受験票は各家庭(もしくはコンビニプリント等)で印刷する
1-4. 受験料
入学検定料(全日制:2,200円・定時制:950円・通信制:無料)はインターネット出願システムの案内に従い、クレジットカード・ペイジー・コンビニ支払いのいずれかで支払います。
1-5. 受験資格
志願者とその保護者が神奈川県内に住んでいる中学3年生であれば、全ての神奈川県立高校および横浜市立高校の中から一校だけ受験することができます。
ただし、市立高校は市外からの入学者数に上限を設けている場合があります。
1-6. 合否の決定方法
評定・学力検査・特色検査の点数をもとに「数値S」を算出し合否を判定します。
数値Sの算出方法
数値Sは、2年3年の評定・3年の「主体的に学習に取り組む態度」の評価・学力検査の得点・学校ごとの調査書・学力検査の比率などによって以下のように計算されます。
| 調査書の評定 |
A =(2年の9教科の評定合計)+(3年の9教科の評定合計)× 2 (重点化しない場合135点満点) ※各教科の[(2年の9教科の評定合計)+(3年の9教科の評定合計)× 2]の数値を、3教科以内各2倍以内で重点化する場合がある Aを100点満点に換算した数値をaとする |
|---|---|
| 学力検査 |
B = 学力検査(実施した3~5教科)の得点合計 ※各教科の得点を、2教科以内各2倍以内で重点化する場合がある Bを100点満点に換算した数値をbとする |
| 観点別学習状況のうち 「主体的に学習に取り組む態度」の評価 |
C = 3年の9教科の「主体的に学習に取り組む態度」の評価合計(重点化しない場合27点満点) ※各教科について評価Aは3、評価Bは2、評価Cは1に換算 ※各教科の評価を、3教科以内各2倍で重点化する場合がある Cを100点満点に換算した数値をcとする |
| 数値S(第1次選考) |
特色検査を実施しない場合 S₁ = a × f + b × g 特色検査を実施した場合 S₁ = a × f + b × g + d × i ※f・gは2以上の整数とし、f + g = 10となるよう設定 |
| 数値S(第2次選考) |
特色検査を実施しない場合 S₂ = b × g + c × h 特色検査を実施した場合 S₂ = b × g + c × h + d × i ※g・hは2以上の整数とし、g + h = 10となるよう設定 |
例を見てみましょう。
調査書の成績が、2年生の評定合計が35、3年生の評定合計が40の場合、a値は以下になります。
A = 35 + 40 × 2 = 115
a = 115 ÷ 135 × 100 = 85.2
学力検査の得点が400点だとするとb値は以下になります。
B = 400
b = 400 ÷ 500 = 80
3年生の「主体的に学習に取り組む態度」の評価が25点だとするとc値は以下になります。
C = 25
c = 25 ÷ 27 × 100 = 92.6
仮に志望校を港北高校とします。神奈川県が発表した公立高等学校入学者選抜選考基準によると調査書・学力検査の比率は以下になります。
第1次選考(評定合計:学力検査):5:5
第2次選考(主体的に取り組む態度:学力検査):2:8
S₁・S₂値を計算すると以下のようになります。
S₁ = 85.2 × 5 + 80 × 5 = 826
S₂ = 92.6 × 2 + 80 × 8 = 825.2
学校によって、評定/主体的に取り組む態度と学力検査の配点比率が異なるため自分の受験する高校がどんな比率になっているか事前に調べておきましょう。
第1次選考と第2次選考
まずS₁ 値を使い募集人数の90パーセントの合格者を決定します。これが第1次選考です。次にS₂値を使って残りの10%の合格者を決定します。これが第2次選考です。
S₁ を算出するための学力検査の比率は5か6の高校が多いですが、S₂の学力検査の比率は8になっている高校が多く、第2次選考は多少評定が足りなくても当日の試験で高得点を取れば合格できる選考方法といえます。
1-7. 倍率はどれくらい?
受験者全体(全日制)の倍率は約1.2倍です。
学校によってばらつきがありますが、ほとんどの高校で志願時倍率が1.5倍以内に収まります。2023年度の入試で倍率が1.5倍を超えたのは偏差値60以上の高校がほとんどで、最も倍率が高くなったのは神奈川総合(個性化コース)で1.92倍でした。
国私立高校との併願のため学力上位高では出願時倍率と実質倍率の差が大きい傾向があります。
| 高校名 | 出願倍率 | 実質倍率 |
|---|---|---|
| 横浜翠嵐 | 2.21 | 1.79 |
| 希望ヶ丘 | 1.51 | 1.51 |
| 新城 | 1.69 | 1.50 |
| 住吉 | 1.62 | 1.51 |
| 多摩 | 2.07 | 1.78 |
| 湘南 | 1.88 | 1.52 |
| 神奈川総合(個性化) | 2.47 | 1.92 |
| 神奈川総合(国際文化) | 1.80 | 1.70 |
| 神奈川総合(舞台芸術科) | 1.97 | 1.87 |
| 横浜サイエンスフロンティア | 1.58 | 1.53 |
| 県立相模原弥栄(スポーツ科学科) | 1.64 | 1.53 |
| 県立相模原弥栄(美術科) | 1.56 | 1.54 |
2. 学力試験について
2-1. マークシート方式
2017年度よりマークシート方式が導入されました。といっても試験問題の全てがマークシート方式になったわけではありません。各科目ともマークシートと記述問題が併用されています。
マークシートはこちらからダウンロードできす。
神奈川県公立高校入試の過去問題まとめ
2-2. 学力検査の平均点と難易度
ここ数年の神奈川県の高校入学試験の平均得点率は55%~60%で推移しています。
| 国語 | 数学 | 英語 | 理科 | 社会 | 5教科 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 (令和5年) |
75.1点 | 53.0点 | 55.3点 | 51.0点 | 58.4点 | 292.8点(58.6%) |
| 2022年 (令和4年) |
61.3点 | 52.9点 | 52.1点 | 58.9点 | 62.4点 | 287.6点(57.5%) |
| 2021年 (令和3年) |
65.7点 | 58.2点 | 54.6点 | 50.1点 | 72.6点 | 301.2点(60.2%) |
| 2020年 (令和2年) |
69.1点 | 55.7点 | 49.4点 | 55.9点 | 58.2点 | 288.3点(57.7%) |
| 2019年 (平成31年) |
59.1点 | 50.3点 | 49.8点 | 61.3点 | 42.5点 | 263.0点(52.6%) |
| 2018年 (平成30年) |
65.6点 | 56.0点 | 56.1点 | 45.3点 | 41.8点 | 264.8点(53.0%) |
| 2017年 (平成29年) |
73.1点 | 63.5点 | 51.9点 | 46.9点 | 54.5点 | 289.9点(58.0%) |
| 2016年 (平成28年) |
64.7点 | 51.7点 | 43.0点 | 46.5点 | 52.0点 | 257.9点(51.6%) |
| 2015年 (平成27年) |
64.4点 | 52.6点 | 51.8点 | 37.4点 | 50.2点 | 289.9点(58.0%) |
| 2014年 (平成26年) |
60.8点 | 51.7点 | 59.6点 | 38.6点 | 49.5点 | 260.2点(52.0%) |
※5教科は各科目を足して算出、()内は平均得点率
国語は5科目で最も平均点が高く60点を下回る年は2019年のみとなっています。
数学はマークシートが導入された2017年は65点と高いですが、その他の年は55点前後で比較的安定しています。
英語も比較的安定していて50~55点で推移しています。
理科は2018年までは30~40点代と公立高校入試にしては平均点が低かったのですが、2019年以降は多少のばらつきはあるものの50~60点前後で推移しています。
社会は2019年以前の50点前後だったのが2020年以降では60点前後と近年難易度が下がっているのがわかります。
3. 面接試験(2024年度から一部特色検査のみ実施)
神奈川県公立高校入試では2023年度まで受験者全員に面接試験が行われていましたが、2024年度は一律の面接はなくなり一部の学校で特色検査の中で実施されることになりました。
4. 受験までにすべきこと
受験までにすべきことは大きく分けて下記の5つあります。順を追って説明します。
- 内申点対策
- 基礎/苦手単元の復習
- 模試を受ける
- 問題演習
- 志望校決定
4-1. 内申点対策
受験を意識した勉強を始める時期にもよりますが、まず最初にすることとは内申点対策です。
内申点は一度確定してしまうと、その後どれだけ頑張ったとしても変えることができません。高校によって目安の内申点がわかっており、もし内申点が足りない場合はハンデを背負った状態で学力試験を受けることになります。
もし、第二次選考での合格を目指すならば内申点は合否に関係ありませんが、第二次選考の枠が募集定員の10%に過ぎませんから安易に第二次選考での合格を狙うのは得策ではありません。
内申点を左右する二大要素は定期テストと提出物です。
定期テストは真面目に授業を受け、テスト前に時間をとって勉強すればある程度簡単に伸ばすことができます。
学校から渡される対策プリントや、兄弟や塾で入手する過去問演習が有効です。
一方提出物は期限までに提出しない、レポートや感想はできるだけラクに済ませる、という習慣がついているとそれを変えるのは非常に難しいです。
一年生の段階では「提出物をしっかり出す。」という習慣を当たり前にしておきたいところです。
4-2. 基礎/苦手単元の復習
これまで勉強をしていなかった人が勉強を始めると、小テストや定期テストの点数はすぐに上がるケースが多いです。
しかしいったん上がるとその後は伸び悩んだり、模試だと得点できないことがしばしばあります。
そのようなケースは(特に国語、数学、英語)基礎の理解がおろそかになっていて、 おもに小学校高学年から中学校一年生にかけての語彙、計算のルール、文法のルールや単語が抜けていまっています。
だから定期テストでは試験範囲を勉強することでそこそこの点をとれていても、模試での得点が伸び悩むのです。
特に中学一年生の数学、英語はなんとなく正解できるのではなくて、どうしてそういうことになるのか他人に説明できるようになることを目指してください。
4-3. 模試を受ける
受験勉強を始めたら、自分の実力がどれくらいかを知るために模試を受けましょう。
志望校が決まっていれば、現時点での自分の学力と合格するために必要な学力のギャップがわかります。そのギャップに直面することで、やるべきことがわかります。
参考記事:
高校受験の模試の活用法【神奈川県】
4-4. 過去問を中心とする問題演習
それまでの勉強で基礎や苦手を復習できたら、入試を意識した問題演習に入ります。
学力検査には科目ごとにフォーマットがあります。
内申点が確定する3年生の秋から冬にかけて過去問や模試の過去問、入試形式の問題集に取り組みます。
出題形式に慣れ、頻出問題を反復練習することで本番まで力を高めていきます。
少なくとも過去5年分の過去問を2回どおりは解いておきましょう。
過去問はこちらから:
神奈川県公立高校入試の過去問題を無料ダウンロード
4-5. 志望校決定
出願をするのが1月なので、最終的にはそれまで志望校をどこにするか決めればよいということになります。
しかし、長い受験をより充実したものにしたいのであれば中3の夏休みが終わるまでには志望校を決めておくべきです。
中3の夏休みは多くの人が基礎や苦手の復習をする段階ですので志望校が決まっているかどうかは勉強内容に与える影響が少ないですし、 夏休み中に気になる高校を訪問したりという活動をすることで志望校について考える機会を得やすいからです。
また、夏休み中という比較的長い期間にまとまった勉強をすることで「自分は頑張った結果これだけ成果が残せるんだ」という実感をもって志望校を考えることができます。
もちろんもっと早く志望校が決まっていてもよいですし、少々遅くなったとしても気にしすぎることはありません。 「志望校が決まっていないから、やる気が出ないのでは?(志望校が決まればやる気が出るはずだ!)」という意見をよく聞きますが、 無理やり志望校を決めさせようとしてうまくいくくケースはほとんどありません。
私たちは、横浜にある小さな個別指導の学習塾です。
受験をはじめとした勉強において、固定的なカリキュラムや決まった勉強方法に生徒を適応させることに意識が向きがちです。
私たちはそれらを大切にすると同時に「生徒」を中心とした学習方法を提案し実践することが、生徒が勉強を楽しむことに繋がり、学力の向上につながると考えています。
「自分に合ったやり方で勉強したい」「どうせやるなら勉強を好きになってもらいたい」という方は是非ティーシャルをご検討ください。


