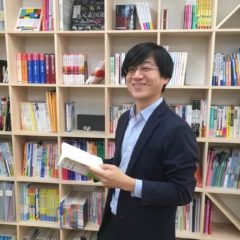世界史の勉強法、および社会の選択科目の選び方

少し前に、世界史の勉強の仕方について書いてのですが、しばらく手をつけずお蔵入りになりつつありました。
しかし、坂本が日本史についてのブログを書きはじめ、また彼が世界史の勉強についても(エントリにあった)本について話をしたことがきっかけで、気合いをいれて書き直すことにしました。
関連記事:日本史の勉強法と、世界史との違い
少しテーマを広げて、歴史科目の選択ということも話題に入れようと思っています。
歴史科目の選択 日本史か世界史か
受験の選択を日本史にするか世界史にするかで迷う生徒さんは少なくないのではないかと思います。私自身はそれほど迷うことなく世界史にしました。
これは単純な理由で2年生になるときに、地理B/日本史Bの選択があり、私は地理を選んでいたからです。とはいえ、別段地理が世界史に役立っていたからということでもなく、日本史が駄目だから、受験校の選択肢が多くなる世界史、という感じで決めました。(第1志望が早慶だったので、確か地理受験はできなかったはず)
よく、どちらの方が覚えやすいかという質問を受けますが、さすがにこれはナンセンスではないかと思います。少なくとも万人に共通の答えはないはずです(あったら全員そっちを選ぶ)。
私の場合、1年のときに世界史Aを必修でやっていたということも関係あると思います。また、その時の先生も、暗記事項の羅列ではなく、事象の背景を大事にするという、世界史の勉強に即した教え方をしてくれる先生でした。
そのような事情もあり、割とすんなりと世界史にするという選択ができたと思っています。選択という言葉は非常に個人の意志力によるところが大きいことを感じさせますが、実際にはそれまでの経歴の積み重ねが大きく影響しているのではないかと思います。
世界史の勉強法
二つの特徴
さて、日本史と比較した時—と言っても、筆者は日本史の受験勉強をしていないのであまり確かなことは言えないのですが—の世界史の勉強とはどんなものでしょうか。
先ほどの坂本の記事に書いてあることをそのままなぞっての発言ですが、やはり①地図の重要性と、②各地域史の並行関係をどれだけ把握できるか、という、ややマルチタスクな性格を持っているのが、日本史と比較したときの世界史の特徴なのかな、と思いました。
地図の重要性
世界史の勉強に関して、私が一番よく覚えているのは、先生に「地図を大事にしなさい」と言われたことです。
私は受験生時代の世界史を、東進の荒巻先生の映像授業で学びました。その荒巻先生がビデオの中で何度も言われていたのが、「地図を自分で描け」ということでした。
すでに勉強している方にとっては当たり前すぎるかもしれませんが、世界史の勉強には世界各地の地名や山河の名前がたくさん出てきます。これらを聞いたときに、パッと頭の中で位置情報が出てこないと、肝心な時系列の話が有機的に理解できない。地図を覚えることが重要なのは、このような理由が旨であったと思っています。
数学でいうところの、サイン、コサインの代表的な値を覚えておく、みたいなところでしょうか。各科目に、このように科目のインフラとでも言うべき大切な土台となる知識があると思います。
世紀感覚を身に着ける
もう一つ、先生がよく言われていたのは、「各イベントや君主の統治期間などを、何世紀のいつごろ、という感覚で捉えるようになりなさい」ということでした。
これは、上に述べた②各地域の並行関係を抑えるという上で必要になるものです。フランス革命は1789年に始まったと覚えると思いますが(今は変わっていたりするのかな)、これを18世紀の終わり頃と覚えることで、「18世紀」という時代がどういう時代だったのかが見えてくるわけですね。
過度な単純化は慎むべきですが、このようにして各出来事を1〜20世紀のいつ頃という形に整理していくことで、全体の見通しがよくなり、世界史の全体像が掴みやすくなっていきます。
より具体的な勉強のサイクル
基礎サイクル
以上が世界史の勉強をする際のコンセプトのようなものにあたるとすると、私も実際にはもっと具体的な勉強のサイクルを回していたはずです。記憶を頼りにですが、参考になるよう、同じ形式で表現したいと思います。
- 映像授業を見る
- 新しい発見があったら書き込み用ノート(専用教材)に書き込む
- 見終わったところの流れを、自分で再現できるか確認する
- A4の裏紙に、ひとまとまりの流れを書き出してみる
- この時、資料集を最大限活用する
- その日やった箇所のストーリーを人に話す
- A4の裏紙に、ひとまとまりの流れを書き出してみる
- 問題を解く
- 見直し
3. の確認作業が、どうやるかで個性の出てくるところかなと思います。人に話すと、自分が意外と覚えてないところ(個々のイベントの因果関係)がわかるので、よかったかなと思っています。
過去問
重要なトピックとして、過去問をいつから始めるか、というのがありますよね。
私は私大専願で、センター試験というものがそこまで大きな比重を占めていなかったので、実はあまりセンターの過去問を解いたという記憶がありません。
いわゆる過去問演習の問題には、第1志望から順々に、終わってしまったら出題傾向が似ている同大学の他学部をやったりしていました(私は早稲田の文化構想が第1だったので、社会科学部の問題を解いていました。文化構想の赤本に「社会科学部は出題傾向が近い」とあったため)。
そのようなわけでセンター対策はそれほどしなかったと思いますが、結果として本番でも1問ミスという喜ばしい成績を収めることができました。全てを確信を持って答えられた訳ではなかったと思いますが、丸つけしている時は正直驚きました。
まとめ
以上が私の思う世界史の勉強の大事なところです。個人的なおすすめを改めて挙げると、
- 地図を把握する
- 世紀感覚を大切にする
- 人に話すことでストーリー理解を確かめる
となるでしょうか。
歴史科目は、闇雲な暗記に走らず、きちんと工夫して力を注げば、その分結果で答えてくれる科目だと思います(どんな科目もそうですね)。
私の場合、教えてくれる先生の魅力(ストーリーの語り方など)にも大いに助けられたと思うのですが、やはり最終的に歴史は好きな科目になりました。
ボリュームも多く大変な科目ではありますが、実りある勉強の一助となればと思っています。
私たちは、横浜にある小さな個別指導の学習塾です。
受験をはじめとした勉強において、固定的なカリキュラムや決まった勉強方法に生徒を適応させることに意識が向きがちです。
私たちはそれらを大切にすると同時に「生徒」を中心とした学習方法を提案し実践することが、生徒が勉強を楽しむことに繋がり、学力の向上につながると考えています。
「自分に合ったやり方で勉強したい」「どうせやるなら勉強を好きになってもらいたい」という方は是非ティーシャルをご検討ください。